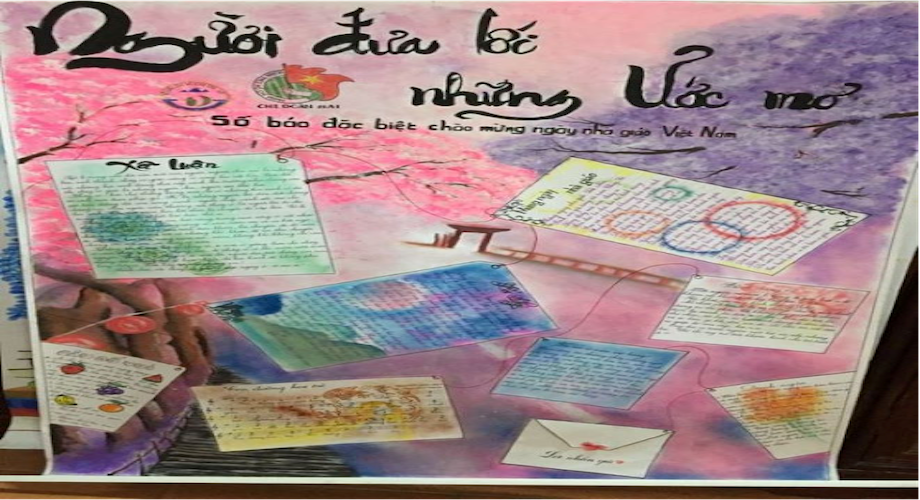東アジア文化における旧暦7月15日の起源と意味
Date: 2025.09.04
意味と起源
旧暦の毎年7月15日(今年は2025年9月6日の太陽暦に該当する)は、「七月十五日」または「中元節」とも呼ばれ、ベトナムをはじめとするアジア諸国の人々の精神文化に深く根ざした重要な伝統行事のひとつです。
この日は「亡者の罪を赦す日」とされ、東アジア諸国の風習において祖先や死者の魂を供養する大切な機会とされています。
民間信仰によると、旧暦7月は地獄の門「鬼門関(きもんかん)」が閻魔大王によって開かれ、死者や霊魂が現世に戻ることが許される時期とされています。このため、旧暦7月は「孤魂の月(ここんのつき)」とも呼ばれ、不成仏霊への供養が広く行われます。
仏教においては、旧暦7月15日は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」として知られ、親孝行を表す特別な日です。その由来は、仏弟子の目連尊者(もくけんれん・Mục Kiền Liên)が、餓鬼道に堕ちた母を救ったという物語に基づいています。
この日に、人々は先祖や両親の恩を偲び、供養を行い、同時に僧侶に食事や布施を捧げ、その功徳を故人に回向することで、報恩と感謝の心を表します。

ベトナムにおける旧暦7月15日の行事
この日、ベトナムの多くの家庭では、祖先を偲び、育ててくれた両親やご先祖様への感謝と報恩の気持ちを表すために、お供え物を準備して供養を行います。
また、「施餓鬼供養(せがきくよう)」として、薄いお粥、米、塩、お菓子などを使って無縁仏(孤魂)に捧げる風習も広く見られます。
寺院では、「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の法要が厳かに執り行われ、読経、回向、赤いバラを胸に飾る「ローズ・セレモニー」、施餓鬼の儀式などが行われ、人々に孝行の心や慈悲の精神を呼びかけます。
さらに、善行のひとつとして、鳥や魚を自然に放す「放生(ほうじょう)」の習慣も広まり、多くの人々が福徳を積む機会としています。

いくつかの国における旧暦7月15日の行事
旧暦7月15日はベトナムだけでなく、アジア各国の文化に深く根付いています。
👉 中国:
亡者の供養を行うこの行事は「中元節(ちゅうげんせつ)」と呼ばれ、ベトナム語では「テト・チュンゴアン」と読みます。中国の仏教徒は旧暦7月の初めから30日までこの行事を行い、主に夕方や夜に催されます。これは、太陽が沈む時にさまよえる霊魂が地獄から解放されると信じられているためです。僧侶や霊媒師は米や小さな食べ物を空中に撒き、霊魂に分け与えます。
👉 台湾:
台湾の「亡者の供養」には古くからの風習として灯籠流しがあり、全国各地で大規模な霊送りの祭りが開催されます。主な催しは、花車や果物を乗せた山車の行列と獅子舞です。
👉 香港:
香港はアジアで最も大きな旧暦7月15日の行事が開催されます。公式の祭典は旧暦7月14日から16日の3日間、全国の寺院や祠で行われ、香港の無形文化遺産の一つとされています。
👉 シンガポール:
シンガポールの盂蘭盆会は、「ゲタイ」と呼ばれる霊魂のためのショーが特徴で、亡くなった親族を偲ぶ機会ともなっています。旧暦7月15日の期間中、チャイナタウンや道教寺院であるLorong Koo Chye Sheng Hong寺院が賑わいます。
👉 マレーシア:
旧暦7月15日は「Hungry Ghost Festival(飢餓霊祭)」として重要な祭りです。人々は祖先への供物として豪華な料理を用意し、大きな人形を燃やし、屋外パーティーやパフォーマンスを開催し、共に祈りを捧げます。
👉 インドネシア:
ここでは「Chit Gwee Pua」と呼ばれ、人々は寺院に集まり、不運な霊に供物を捧げます。供物はその後貧しい人々に分けられ、ジャワ島の祭りでは供物を巡る争奪戦が恒例となっています。北スマトラ、リアウ、リアウ諸島では、マレーシアやシンガポールの華人コミュニティの伝統に倣ったゲタイの舞台も開催されます。
👉 日本:
旧暦7月15日は「中元(ちゅうげん)」とも呼ばれ、この期間に「お盆」として仏教の祭りが行われ、先祖や故郷への感謝を表します。祭りは約3日間(旧暦7月13日から15日まで)続きます。
👉 韓国:
韓国では旧暦7月15日を「백중(ペクチュン)」または「백종」と呼び、「百種類の穀物」を意味します。この時期は多くの野菜や果物の収穫期にあたります。また中国と同様に「中元節」や「盂蘭盆(ウランボン)」とも呼ばれています。

(ソース:民族と発展新聞)
人間的な価値
旧暦7月15日は、先祖を偲び、親への感謝を表すだけでなく、迷える霊魂に対する慈悲や分かち合いの精神を広める機会でもあります。
これは長い歴史を持つ美しい文化であり、ベトナム人をはじめアジアの人々の精神生活において、孝行の道徳を育み、地域社会の絆を深める重要な役割を果たしています。