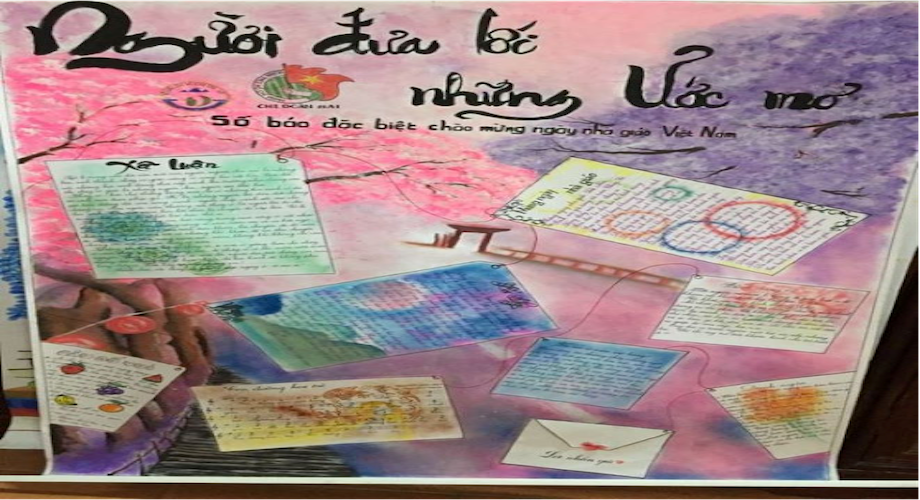七夕(旧暦7月7日)– 東アジア文化が色濃く反映された伝統的な行事
Date: 2025.07.16
七夕は旧暦の7月7日に行われる行事であり、本年(2025年)は8月29日(グレゴリオ暦)にあたります。このお祭りは中国発祥の伝統行事ですが、ベトナム、日本、韓国など東アジア諸国でも広く受け入れられています。
七夕は「雨季の節句(テット・ガウ)」あるいは「雨夫婦の日」とも呼ばれます。この行事は、牽牛と織姫という切ない愛の伝説に結びついており、恋人たちの間での待ち続ける心、忠実さ、そして愛のための犠牲を象徴する物語です。

♥ 起源と意味
伝説によると、牽牛(けんぎゅう)という心優しい牛飼いの青年と、天の機(はた)を織る織姫(おりひめ)は深く愛し合っていましたが、天界の掟によって引き離されてしまいました。二人は年に一度、旧暦7月7日の七夕の夜にだけ、カササギ(オウチョク)の群れが天の川に橋をかけてくれるおかげで再会することができるのです。
このように、七夕は単なるスピリチュアルな行事ではなく、一途な愛や永遠の絆を称える日でもあります。東アジアのいくつかの国では、この日を「恋人の日」としても捉えています。
♥ 習慣と活動
・ベトナムでは、七夕は大きな祝日ではありませんが、若者の間では注目されています。多くのカップルが一緒にお寺に行き、良縁や永遠の愛を願います。また、「この日に赤豆のおしるこ(チェー・ダウ・ドー)を食べると恋がうまくいき、運命の相手に出会える」との言い伝えもあります。
・中国、日本、韓国では、七夕にはさらに多彩な活動が行われています。例えば、日本では「七夕(たなばた)」と呼ばれ、短冊(たんざく)という小さな紙に願い事を書き、竹の枝にカラフルな飾りとともに吊るします。中国では、女性が手芸や織物の技を競う風習もあり、天に供え物をして幸せな恋や結婚を祈るのが一般的です。
・中国ではこの伝統行事は、未婚女性が愛や結婚の幸せを天に祈る機会でもあり、また自然や才能ある女性への敬意を表す日ともされています。「恋人たちが七夕の夜に織姫と牽牛の星を一緒に見ると、永遠に結ばれる」とも信じられています。また、独身者がこの日に赤豆のおしるこを食べると、近いうちに恋人ができるという言い伝えもあります。
・日本では、この日になると牽牛と織姫が天の川を渡って再会するとされています。七夕には、人々が短冊に願い事を書き、竹に飾りとともに吊るします。これによって願いが叶うと信じられています。Tanabata(たなばた)は個人の夢を表現する機会であると同時に、日本文化における自然、伝説、信仰が調和する美しさを象徴しています。この時期、日本の夏の夜は華やかでロマンチックな雰囲気に包まれ、観光客にも人気のイベントです。
・韓国では、七夕は「チルソク(칠석)」と呼ばれています。この日には、人々が健康を祈願して水浴びをしたり、小麦粉を使った麺や焼き菓子を食べたりします。チルソクは「小麦料理を楽しむ日」としても知られており、この日を過ぎると冷たい風が吹き始め、小麦の風味が損なわれると考えられています。

(出典:民族発展新聞)

(出典:Báo Mới)
♥ 七夕の日に「すべきこと」と「避けるべきこと」
► すべきこと:
・お寺参り: 自分自身と家族の平安・幸運を願ってお寺に参拝します。独身の人は縁結びを願い、理想の相手に出会えるよう祈るのが一般的です。
・善行を積む: 可能であれば人を助けたり親切な行動を取ることで、徳を積み、良縁や幸運が訪れると信じられています。
・ランタンを飛ばす: 恋人たちは永遠の家庭を願って灯籠を飛ばし、独身の人は運命の人と出会えるようにと願いを込めます。
・プレゼントを贈る: 多くの若者がこの日、大切な人にプレゼントを贈って想いを伝えます。
・赤豆のおしるこを食べる: 特に独身者の間では「恋人ができる」と信じられており、縁起を担いで食べる習慣があります。
► 避けるべきこと:
・婚約や結婚式を挙げること: 昔からの言い伝えでは、牽牛と織姫が再会してすぐにまた別れてしまう日とされ、不吉と考えられています。
・家を建てたり車を買うこと: この時期は旧暦7月で雨が多く、物事を始めるのにふさわしくないとされています。
・悪いことをすること: 徳を損なうような行動は避け、恋愛運や運勢を良くするためにも善行を心がけることが大切です。

♥ 人間味あふれるメッセージ
七夕は恋人たちの愛を称えるだけでなく、すべての人間関係において「忍耐」「誠実さ」「犠牲の精神」の大切さを思い出させてくれる日でもあります。
たとえ時間や距離に隔てられ、どんな試練があろうとも、互いに真心を持って向き合えば、いつか願いは叶うという希望を私たちに教えてくれます。